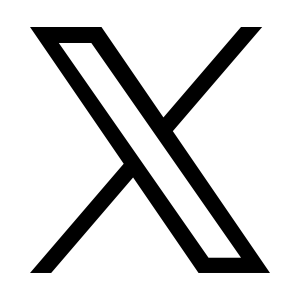LEADERS BLOG
例えば「この箱がこの場所に置いてあると邪魔(危ない)であり、安全な場所に移動すればよい」状況において、邪魔ではないか?を問う場面があったとします。
回答パターンがあって、
①あ、本当ですね。(邪魔だという認識がない?)
②邪魔だと思ってたんですよね。(認識しているのに何もしてない)
③ ②+どうすればいいですか?(一応、解決策を聞いてくる)
私の心の中は、
①は、いつか死ぬよ、あんた…。
②は、思ってただけ?他人事?
③は、自分の考えはない?もしくは移動先の相談してほしかったな。
そもそも先読みして行動力ある人(思いやりもある人)は
④気づく前に解決してくれている
すなわち、問う場面がそもそも発生しないことになります。
④を日常的にしている人は、
誰かがやってくれるだろうとか、誰かに評価されたいとか、損得勘定がなく、
当たり前だと思っている人。
ただし、④については、そのようなことがあったことすらわからないわけですから、
気づいてあげられないので、「ありがとう」が伝えられない。
ですので、④の皆さんに伝えたい。
「いつもありがとう、感謝です!」
フィクションですと池井戸潤の作品が好きです。
特に好きなのが「下町ロケット」です。
(コテコテの熱い系・痛快系が好きですね)
本も読みましたが、ドラマも見ましたが本当に面白かったですね。
吉川晃司演じる帝国重工の財前部長、いいですよね。
無人農業ロボットを巡る問題で、窮地に立たされた佃製作所を助けるため、財前が帝国重工の経営陣を説得するシーンでのセリフで、
「世の中のために、救えるものであれば手を差し伸べる。それが、わが社が担うべき責任であるべきです」
くさいセリフですけど、好きですね。
このセリフは、企業としての利益だけでなく、困っている人々を助けるという大きな使命を訴えるものでした。信念を貫く覚悟ですね。
わが社に置き換えると「世の中の人にいい商品だと思ってもらいたい」
この想いは間違いないです。
私たちの商品で最後を送り出すことができて本当に良かったって思われたいです。
きれい事かもしれませんが、
「いくら利益をもたらそうと、不誠実なものが誠実なふりをすれば、会社は乱れる」
ビジネスの世界にいながらも、利益や立場を超えた「正しいこと」を追求するという「誠実であること」の大切さを下町ロケットでよく描いていると思います。(池井戸節!)
日々、今の自分(行動)は「誠実なのか?」と自ら問い続けていく人でありたいですね。
私がずっと見たかった中国の10年「再会長江」という映画。
昨年日本でも上映されてましたが行くことができず、最近やっと動画配信されたので見ることができました。
映画の冒頭から、長江の源流へと誘われます。まだ人跡未踏の秘境に広がる、想像を絶する大自然。
氷河が溶け出し、細い流れがやがて大河となるその過程は、生命の誕生と成長を目の当たりにしているかのようです。
ドローンで捉えられた映像は、その雄大さを余すところなく伝え、思わず息をのんでしまいました。
しかし、この映画の真骨頂は、美しい映像だけではありません。
10年前の撮影と、現在の撮影を比較しながら進んでいく構成が、時間の流れ、変化、そして不変というテーマを鮮やかに浮かび上がらせます。
そして、その中でも私の心を鷲掴みにしたのは、雲南省奥地の「シャングリラ(香格里拉)」と呼ばれる地です。
切り立つような山々の間に広がる、どこまでも続くかのような緑の絨毯。
そこには、現代社会の喧騒とは無縁の、原始的で、しかしとてつもなく豊かな自然が息づいていました。
(言葉では伝えづらいので、是非ネットで検索してみてください)
そして、そのシャングリラで出会った一人の少女の存在が、この映画にさらなる深みを与えています。
その少女は地元の世界しか知らず、地下鉄にも乗ったことがなく、家族と一緒に大都市・上海へ連れて行き、外の世界を初めて目にした瞬間を動画にしています。
それは10年前の撮影で、無邪気な笑顔を見せていた彼女が、10年後、どのように成長し、長江と共に生きているのか・・・。
※ネタバレになるので10年後の彼女がどうなったのかは是非映画を見てください!
ということで、10年越しのドキュメンタリー映画を見て、
長江という一本の河を通して、ダムの建設、都市の発展、人々の生活様式の変化…。文明の進歩と自然との共存という、根源的な問いを投げかけられているようでした。
今まで一生のうちに行きたい場所といえば「少林寺」でしたが、
今は「シャングリラ」をこの目で見てみたい!
皆さんも一生のうちに行ってみたい場所はありますか?
最近、ネットでも話題になっている「アレクサンドラ構文」を知っていますか?
やったことがない人は是非下記を答えてみてください。
(以下、引用)
Alexは男性にも女性にも使われる名前で、
女性の名前Alexandraの愛称であるが、
男性の名Alexanderの愛称でもある。
間:この文脈において、以下の文中の空欄に
当てはまる最も適当なものを以下から選べ
Alexandraの愛称は( )である。
① Alex
② Alexander
③ 男性
④ 女性
皆さんの答えはどうでしたか?
ちなみに公立の中学生で正解率38%、進学校の高校生で正解率65%だそうです。
「文字は読めるが文章が読めない」は「機能的非識字」というそうです。
また、自分が「機能的非識字」であると自覚がない人も多そうです。
確かに、頭の良い人たちが作った法律などはアレクサンドラ構文のような文章がいくらでもありますよね。
たとえその情報を知ったとしても、内容を正しく理解できないことで社会生活で弊害が出てしまい損してしまうことも多いかもしれません。
もはや損していることすら気づいてないかもしれないですよね。
ちなみにこの問題、私は正解しました。(勘ぐったり引っ掛け?ではと猜疑心ありありで全く自信なかったですが・・・)
正解は①
しかし、「アミラーゼ構文」という別の問題もあるのですがそれは不正解でした・・・恥
やったことない方は是非ネットで検索して解いてみてください!
先日ウーピー・ゴールドバーグ主演の映画「天使にラブソングを」を久しぶりに見ました。
皆さんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。
90年代前半くらいの映画で、もう30年以上も前の映画になるのですね。。
さて、この映画ですが、犯罪を見てしまったデロリスを匿うために教会のシスターとして送り込み、その教会のシスター達の下手極まりない聖歌隊に歌の指導をして、最後にはローマ法王が聖歌隊コンサートを見に来るというストーリー。
久しぶりに見るとデロリスのリーダーシップ力が凄い!と私なりに感じて、考察してしまいました。
[デロリスの聖歌隊を指導するアクションとその効果]
・皆の歌声を聞いて、バラバラの配置からアルトやソプラノなど担当エリアを分けて、まず歌わせてみる
→現状を把握し、体制を整える「現状把握」と「体制整備」
・担当エリアを変えただけで、音を合わせることができるようにはなった。しかし揃ってはいない。
→まずできたことを褒めて「成功体験」、全体や個々にダメなところも指摘する「チームワークの重要性」「課題解決」
・デロリスの指導で皆がもっとうまく歌えるようになりたいと思い、シスターたちが自主練を始める。
→スキルアップのための「モチベーションアップ」と「自己学習型」人材への意識変化
・デロリスの指導のもと初の聖歌隊コンサートにて伝統的な歌い方とパフォーマンスなど現代風アレンジの歌い方をお披露目する
→現状(既存べき論)から問い直し「新しいことへのチャレンジ」、結果として教会に興味を集め「PR効果」により人が集まり、集客力アップ「集客効果」
・聖歌隊が評判となり、教会に人が集まるようになった。メディアにも取り上げられ、チャリティーコンサートで寄付も多く集まって老朽化した建物の修繕も可能になった。
→「知名度アップ」「収益アップ(経済効果)」
等々、他にもいろいろな名シーンがありますが、
デロリスのリーダーシップ力、コミュニケーション力、そして何といっても「信頼を勝ち取る力(人間力)」が素晴らしいなと。
現実は映画みたいにうまくはいかないのは百も承知ですが、明日も頑張ろうと元気をもらえる良い映画だなとあらためて思いました。
- 2025.12
- 2025.11
- 2025.10
- 2025.9
- 2025.8
- 2025.7
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6