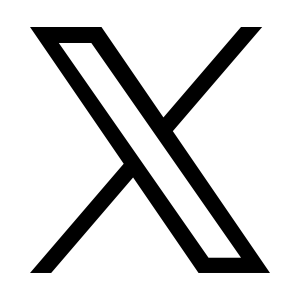LEADERS BLOG
「今度、名古屋で集まるんだけど来ない?」
そんなふうに声をかけられたのは、集まりの3日前のことでした。まぁまぁ忙しい時期だったけれど、その日はぽっかり1日空いていて、久しぶりにゆっくりしようと思っていた日。これまでの自分なら、きっと断っていたと思います。
でも最近、自分と向き合う時間が増えたことで、仕事以外のこともちゃんと大事にしたいと思うようになっていました。疲れていたし、正直そこまで乗り気ではなかったけれど、「まぁ、断る理由もないか」と、なんとなく流れに身をまかせて行ってみることに。
当日は久しぶりの再会もあり、16時のオープンから22時まで、ビアガーデンで6時間ぶっ通しで飲みました。まるで学生みたいな飲み方。仕事の話から学生時代のエピソード、最近気になっていることまで、ただ笑って話しているだけなのに、あっという間の時間でした。ただただ、いい時間だったなと。もちろん翌日は少し大変でしたが、参加して本当によかったと思っています。
それ以来、「誘われたら行ってみよう」という気持ちが、少しずつ育ってきました。予定していなかったことに身を委ねると、先のことを考えすぎないことの大切さにも気づかされます。
興味があることだけを選びがちだったり、意味を考えすぎて踏み出せなかったり。いつの間にか、予定調和じゃない出来事を楽しむ力が、少し弱っていた気がしました。
大げさかもしれませんが、“自分からは選ばなかった出来事”が、新しい自分と出会わせてくれるのかもしれません。
2019年7月にスタートした「リーダーズブログ」は、新たにホームページを立ち上げたのを機に始めました。
約300回の投稿を重ね、私自身も今回で50回目となりました。このタイミングで過去の投稿を振り返ってみようと思います。
全部読んでみてわかったことは、「ひつぎひつじ」や「Rotch」の話題が多いこと、テーマに困ったんだろうなと思う内容も多々ありました(笑)
その時の関心と思考が分かり、当時の記憶が蘇り新鮮な気持ちになりました。
その中でも何をテーマにしてるんだろうというこの2つのブログ
2022年2月25日「初老を過ぎて発見した『分け目』」
2022年8月8日「人によって違う心地良さ」
この話に共感していただける方とは、ぜひゆっくりとお話ししたいです。
約300回の投稿を通じて、三和物産の歩みと役員の想いを発信してきました。
今後も私たちが感じていることをコトバにし、皆様と共有していきたいと思います。
ぜひ、これまでの投稿を通して三和物産の成長と変化を感じていただき、今後も私たちの歩みを見守っていただければ幸いです。
皆さん、自分のくちぐせって意識したことありますか?
気がつくと、何かを見たり聞いたりしたときに「これ、面白い!」とか「うーん、ちょっと面白くないな」と言ってしまう私。便利な言葉ですよね、「面白い」って。だけど、これって実は聞く側には曖昧すぎるかも?とふと思ったんです。
たとえば、仕事で誰かの企画に対して「そのアイデア、面白いね」と言うと、一瞬喜ばれるけど、「どこが?」と内心で思われることもありますよね。具体的にどの部分が面白いのか、どう感じたのかを言葉にしないと伝わらないなぁと気づきました。
逆に、「○○な視点が新鮮で面白い」とか「その発想が他にはないところが面白いね」と伝えると、相手はきっと「あ、そこを見てくれたんだ!」と嬉しく感じるはずです。そして、「どうしてその発想が浮かんだの?」と問いかければ、相手の考えをさらに深掘りできて、会話も広がりますよね。これまで何度も「面白い」で終わらせてしまったのは、もったいなかったなぁと反省しました。
恐らくこれからも「面白い」とつい言ってしまうと思うので、何が面白いのかを意識して、きちんと言語化していきたいと思います!

神奈川県の高校2年生に授業をしてきました。 テーマは「Futures Literacy 複数形の未来と意思決定」というちょっと難しそうな授業。
テーマを聞いて、葬祭用品メーカーが高校生に何を話そうかなぁって迷いました。「死」とか「別れ」って、普段あまり話題にしないテーマですよね。特に若い人たちにとっては、なおさらです。だからこそ、未来の意思決定の際に「死」や「別れ」を通して面白い観点や問いを投げかけれるんじゃないかと思いました。そこで「誰にでもいつかくる終わりについて考えることで、人生のヒントが見つかるかも」をメインメッセージにして話してみることにしました。
授業では、三和物産が目指してきた「もっとカジュアルに死から生を考えてもいい社会」を表現した商品やサービスを中心に紹介しました。 特に「ゆめだっこ」や「雲もなか」は反応が想像以上に良かったです。生徒たちからは「死について前向きに家族と話してみたい!」とか「周りの人への感謝の気持ちを大切にしたい!」なんて感想をもらいました。
あと、就活生向けに企画した「死ンキング展」の、一部のコンテンツを体験してもらいました。
未来のことを考えるとき、実は「死」や「別れ」について考えることで、自分にとって本当に大切なものが見えてくるんです。これって、未来を選ぶときのすごく大事なヒントになると思うんです。「死」や「別れ」を扱う会社だからこそ、未来をよくするための観点や問いを発信することができる。今回授業をして、改めて面白いこととがまだまだできる可能性を感じました。

現在、日本最大規模の公募広告賞である「第62回宣伝会議賞」において、『棺のことを考えて、わくわくしませんか?』をテーマに、皆様から「桜風」を世の中に知ってもらうためのキャッチコピーを募集しています。
「宣伝会議賞」をご存じでしたか? 私は14年前に三和物産に入社したときは、まだ賞のことを知りませんでした。きっかけは、三和に入社し配属されたのが企画部だったことです。経歴としては営業のみだったので、右も左も分からない状況の中で学びのために少しでも良質な広告や企画のヒントを得ようと手に取った一つが宣伝会議でした。
その中でも「宣伝会議賞」で選ばれたキャッチコピーは、私の心に深く刺さるものばかりで、強い衝撃を受けました。自分でも「こんなキャッチコピーを作ってみたい!」と思い、応募を真剣に考えていた時期もありました。
「宣伝会議賞」をご覧になったことがない方は、ぜひ一度、歴代のグランプリに選ばれているキャッチコピーをチェックしてみてください。私も歴代のグランプリ作品を見返しましたが、「これはすごい!」と思うコピーは当時と同じでした。機会があれば、私の心に刺さったコピーを当ててみてください。
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6