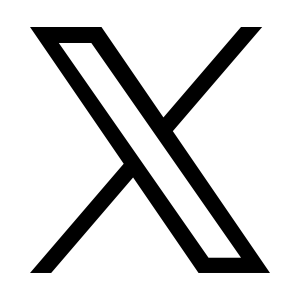LEADERS BLOG
新聞に小学校2年生女の子の「水田」という習字と「すてきな色ばかりのけしき」という習字の説明文が掲載されていました。
そこに合った言葉を拾ってみると
「よいお天気」
「空は水色」
「山はみどり色」
「ゆきで白色」
「水はとうめい」
「水がつめたかった」
「水田はゆきどけ水がつかわれている」
「すてきな色ばかりのけしきを見ることができて、しあわせな気もちになりました」
簡素な言葉と限られた漢字の文章はとても読みやすく、純粋で心が澄んでいく気がしました。
きっと美しい透明な心があれば知っている言葉は少なくても感じていることは正確に伝えることができるんだと思いました。
ひらがなとその合間に点在するシンプルな画数の少ない漢字の配置すら不思議にきれいに見えてきました。
『学問のすすめ』といえば?
はい、そうですね。1万円札の肖像にもなっている福沢諭吉さんの代表的な著書の一つです。冒頭の一句
【天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言えり】
はあまりにも有名で、これをもって博愛・平等・人道主義を賛美した内容かと思いきや、その後に続くコトバはあまり知られていません。ちょっと抜粋してご紹介しますね。
【されども今広くこの人間世界を見渡すに、賢き人あり、愚かなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや?その次第甚だ明らかなり。実語教(当時子どもがよんでいた教科書的なもの)に、人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なりとあり。されば賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとに由ってできるものなり】
と続きます。
つまり、人間は生まれた時には貴賤はないけどその後の人生で学ぶことをするかどうかで大きく差がついてくる。だから学ぶことに於いては差別があってはならない。と解釈できると思います。ちょうど封建制度が瓦解して新しい世の中になったけど、まだまだ身分的な差別があった当時(明治時代初期)の世相を反映した内容ですね。
さて、今の日本は誰もが自由に学問ができる環境です。つまり誰もが賢人になれる(可能性がある)環境ということです。このあたりまえの前提を感謝しつつ、学問を通して世の中を広く深く知り、新しい知恵(イノベーション)や他人と議論する勇気(変革)を得て、豊かに楽しく生きていこうぜ!
と、財布の中の諭吉クンが語りかけている気がしませんか?
ではまた!
いよいよ新年度66期が始まりました。
3年ぶりのリアル全体会議が開催され、久しぶりに本物の?顔を見れた仲間もいた事でしょう。
やはり、モニター越しに話をするのとは違い、しっかりと想いが伝わったことと思います。
さて、65年という社歴を終え66年目をスタートさせるにあたり、皆さんはどの様に」感じるでしょう。人間でいえば66歳・・・ 定年を過ぎ、やっとこれ
から自分の人生を謳歌することができるようになり、何をしようか・・趣味に没頭しようか・何か社会の役に立つことを始めてみようか・いやいや、まだまだ体も丈夫だし、もっと働きたい・・などなど色々だと思います。
会社の寿命は人間と違い限りがありません。常に成長し、社員という家族の頼りになる拠り所であり続けるのです。
創業当時からその拠り所を創り上げて来てくれた諸先輩方の努力と想いを引き継ぎつつ、当社で人生を創り上げるであろう今と未来の社員のために、次の65年をこれまでに負けないくらい素晴らしい会社に皆で育て上げようではありませんか!
きっと「あの当時の先輩たちがいたから今がある」と言ってもらえると思いますよ!!
今年度も三和スピリットを拠り所に、目標達成に向かって頑張りましょう!!

「誠人 ニュース見たぞ!えらい」
先日リクラのニュースがテレビで流れた後、
中学時代の恩師からメールが来ました。
中学時代にあこがれていた尊敬できる恩師(陸上部の顧問)。
実は、この先生みたいになりたくて、大学まで教員目指していました。
懐かしい記憶が蘇ってきました。
当時、先生からよく聞いた言葉が
「ナマクラするな!」
「ナマクラするやつは、大人になってもナマクラする」
※ナマクラは方言で怠けてばかりいる。だらしがない。
「先生がいるときは、一生懸命やる生徒と
見ていない時に怠けている生徒はすぐに分かる」
なんとか先生に認めてもらいたかった私は、
練習で手を抜けなかったのを覚えています。
そんな先生に修学旅行の時に、
「誠人は大人になったらもてる」
何を根拠にそんなことを言われたのか分かりませんが、
初めて認められたと感じたコトバでした。
今でも嬉しい記憶です。
恩師に近づけたのか分かりませんが、
あの人みたいになりたいと頑張っていた中学生でした。
以前書いたリーダーズブログ
「あこがれる人がいる会社」→リンクhttps://www.sanwa-bussan.co.jp/leaders_blog/2019/08/
3年前から比べると、三和物産にも魅力ある人材が
たくさん増えたな~と思います。
いい流れができてきたかな。
日本の葬儀の意味合いは通常、遺族や近親者が故人の死を受け入れ、儀式としてお別れし、区切りつけることで明日に向かうことと考えられます。
テレビで見たのですが、エリザベス女王の葬儀に対してイギリスでは宗教観が異なることもあり「女王のこれまでの人生を祝福する」とインタビューに答えていた一般市民の声に少し驚きました。
日本でも葬儀に際して故人への感謝を表しますが「祝福」という捉え方はほとんど無いと私は思っています。
死は言うまでもなく哀しいことですがその人の一生を祝うことに全く違和感はありませんでした。
少なくとも真っ当に(何をもって真っ当というかは人それぞれですが残された人がそう思えればいい)生きてきた人の一生を祝うことで哀しみを少し軽減できるはずです。
異なる文化を知ること、特に「祝福」を葬儀の一テーマとすることで改めて葬儀の在り方を捉えなおして、新たなグリーフケアにもつながるこれまでとは違う「別れのカタチ」を創造できるのではないかと感じました。
- 2025.12
- 2025.11
- 2025.10
- 2025.9
- 2025.8
- 2025.7
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6