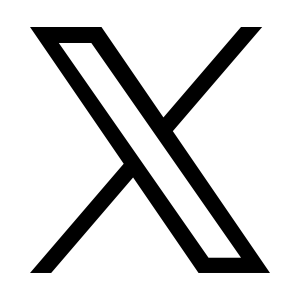LEADERS BLOG
家内が10年ほど前に、1年半近く飼い主のいない生活を送っていた猫をもらってきました。
オレンジっぽい茶猫なのでオーレンといいます、名付け親は不明です。
あまり愛想のないマッチョな雄猫で、私の近くに来ることもなく、またペットということでもなくただ同居しているという感じでした。
その関係は時が経っても変わらなかったのですが、2ヶ月ほど前より鼻がグズグズでよくくしゃみをするようになり、家内が動物病院で診てもらったところ、鼻の上の方に癌があるが高齢なので手術もできないという。
食も細くなりマッチョだった身体は痩せてしまい、毛も艶がなくバサバサになってしまいました。
ここ1ヶ月は鼻血を垂らすようになり、よく見ると目からもうっすら血を流すようになりました。
ただよろよろとしながらもちゃんとトイレには行って排泄はします。
止血剤や抗生剤で治療しており、家内が家でも栄養剤を点滴し、針を刺されても意外と大人しくしています。
私も家にいる時は鼻血を拭いてやったり、時おり撫でたりしてしていたら、最近は私の近くに擦り寄ってくるようになりました。
そうなると可愛いもので膝の上にのせてやったりしているうちに友人のように感じるようになりました。
誰にも不満も不安も言わずに静かに過ごしています。
もうしばらくすると亡くなるという医者の見立てです。
命あるものが最期まで懸命にけなげに生きようとする姿は凄いなと思ってしまいます。
もっと早く友人になれれば良かった、、、
あの鼻血が詰まった顔をもう少し見ていたいなと思います。
以前に三和に社内報があった時にも載せましたが、
子供の頃はとにかくカンフー映画にはまり、とにかくジャッキー・チェンの映画が大好きでした。
当然ながら小学生低学年頃はビデオデッキが家になくテレビや映画館に見に行くしかなかった。
今や時代も進化して、ブルーレイやネットに変わり、当然我が家にもいつの間にかビデオデッキもなくなって、その当時録画したものも見られなくなってしまいました。
(皆さんは家にあるビデオテープってどうしていますか?)
先日、ジャッキーの映画をまた見たくなってアマゾンで少林寺木人拳くらいから大人買いしてしまいました。(ヤングマスターくらいから毛色が変わって見なくなりましたが)
この年で改めて映画を見ると「・・・」
①ストーリーは大体「かたき討ち」
②ボスを倒したらすぐに「終劇」で全く余韻がなく終わる
③ジャッキーが急に二重になっている(どうでもいいか)
何か子供の頃のトキメキもなく味気ないとさえ感じてしまいます。
※少林寺木人拳に至っては木人の動きに思わず笑ってしまいました。
なるほど、今思えば子供の頃はストーリーなどには全く興味がなく、蛇拳とか酔拳とかカンフーの「動作」に釘付けで、それを「真似したい」「自分もできるようになりたい」というのが目的で見ていたのだなと。
当時、親に「カンフー」が習いたいと言って「そんなところ日本にないわ!」と一蹴されたことを思い出しました。
大人になると子供の頃の純粋な視点、理屈なんてなくワクワクする気持ちがいつの間にかなくなってしまっているのですね。
皆さん、今「ワクワク」することって何ですか?
「そんなはずではなかったのに・・・」
「なんでこんなことになったんだろう・・・」
と嘆き怒りそして悲しみに暮れること、皆さんも経験があると思いますがいかがですか?
僕はけっこうあります(笑)
例えば、
電車が遅延して遅刻した
上司の指示どおり行動したのに叱責された
部下が仕事でミスをしてお客様からの信頼を失ってしまった
子どもが走り回って他人のモノを壊してしまった
雨が降ってイベントが中止となった
伝染病が流行して旅行に行けなくなった
などなど。
このような「想定外」の出来事ってよくあるハナシです(少なくとも僕は)。
「想定外」。嫌なコトバです・・・。
でもこの「想定外」を意識的に作ったり楽しんだりするケースがあります。それは「旅行」です。特に言葉も文化も違う国へ行く海外旅行なんて最たる例です。あえて、不安・恐怖・混乱・不合理・怒り・失望・・といった居心地の悪さを大金と時間をかけて体験するなんて不思議なものですが、それが旅の醍醐味だと僕は考えています。
あれ?
もし日常生活でもそんな「想定外」を楽しむことができたら?
そういう境地で生活できれば心穏やかなHAPPYな生活が送れるのでは?
これは試してみる価値があるかも!
ということで、皆さんからの「想定外」なご相談やご提案、お待ちしております!!
ではまた!
令和5年に入り、瞬く間に1ヶ月が過ぎました。
歳を重ねるごとに1年が加速度的に早くなっているように感じます。皆さんはどうですか?
ところで、2月は「如月」とも言いますが、何故か・・
ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、如月(きさらぎ)は「衣更着」とも書きます。
まだまだ寒が厳しい季節に「衣を更に着る」月であるという事から「き-さら-き」と言い
ます。
金沢も1月下旬に26年ぶりの-6度を記録したようで、久しぶりに気温も低く雪も残っていま
す。
まだまだ寒い日が続きますが、体調は万全にして日々を迎えたいと思う今日この頃です。

みなさんはRADWIMPSさんの「正解」という楽曲を聞いたことがありますか?
2018年にNHKで放送された「18祭」という番組のために作られた曲で、
Youtubeでも1,000人の18歳が合唱している様子が紹介されています。
→https://youtube.com/watch?v=xKjFYKWCDas&si=EnSIkaIECMiOmarE
その放送を当時見て感動したことを今でも覚えています。
ただ、その時は18歳の若者たちの感情あふれる合唱する姿に心を打たれていました。
それから月日が流れ、昨年度末のテレビ番組で、
久しぶりに「正解」が紹介されているのを見ました。
そして、その紹介されている歌詞を見ると、改めて感動したのです。
特に刺さった歌詞は、
「あぁ 答えがある問いばかりを教わってきたよ そのせいだろうか
僕たちが知りたかったのは いつも正解など まだ銀河にもない
一番大切な君と 仲直りの仕方 大好きなあの子の心の振り向かせ方
なに一つ見えない 僕らの未来だから 答えがすでにある 問いなんかに
用などはない」
【RADWIMPS 正解(18FES ver.) 作詞:野田 洋次郎】
18歳はとうに過ぎたおっさんの私ですが、
おっさんの私にもこの歌詞が刺さりました。
歌詞は、年齢や立場や環境が変わると、
またいろんなことを考えさせてもらうのだと感じました。
昔好きだった楽曲、今流行っている楽曲、思い出に残っている楽曲…聞き流すばかりではなく、少し歌詞にも耳を傾けながら聞いてみようかなと思っている今日この頃です。
みなさんの心にグッとくる歌詞は何ですか?
- 2025.12
- 2025.11
- 2025.10
- 2025.9
- 2025.8
- 2025.7
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6