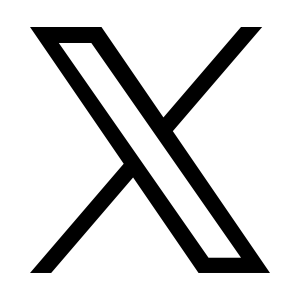LEADERS BLOG
ずっと以前に家の洗濯機が壊れて買い替えたことをブログでも掲載したと思います。
最近、冷蔵庫の調子が悪く電気屋に見に行きました。
洗濯機と同じで、進化していますね冷蔵庫も・・。
色々と機能が充実しているのはわかりますが、それにしても高いなと。
結局その日は決められなかったので、冷蔵庫のことをネットであれこれ検索していると
「冷蔵庫 補助金」というワードが出てきたので、どういうことかと見てみました。
あるのですね。冷蔵庫を買った時の補助金。
知りませんでした。
(ただし我が家の自治体は対象外でした。残念)
ただ、やはりこういうことって知っているか知らないかで随分損しますね。
色々調べてみると、自治体によっては、ランドセル購入、市販の薬を買う(セルフメディケーション制度)、電気自転車購入、禁煙治療、ベビーカー購入などなど・・・利用しない手はありませんね。
自分で調べること、知ることって本当に大事ですね。
皆さんもお住まいの自治体でどんな補助・助成制度があるか是非調べてみてください。
申請しておけば良かったと後悔しないためにも。
テレビで観られた方もいるかと思いますが、那覇から20キロ離れた前島という離島で一年の半分は家族と離れて一人で暮らしている85歳の男性の話です。
その島には元は島民が居たようですが、台風の大きな被害で住めなくなり皆が移住し、その男性も那覇で生活していました。
高校生のころから前島に戻りたいと思うようになり、65歳でその島を復興しようと様々な野菜などの栽培に挑戦しましたがうまくいかなかったとのこと。
飲料水や主要な食べ物は那覇から買出しているが、飲水以外は雨水、湧水を使い、電気はソーラーパネルを使って、彼なりに問題無く生活しています。
昼は海を見ながらカップ麺を食べたり、午後は毎日ジャングルような森を散歩(探検!?)、夜は晩飯の食材をのんびり釣る。
健康に長生きすることが彼の大事な価値観だと語る。
それには空気がきれいで心が洗われて、自然を感じながら生きていける前島での生活が一番だと。
老人のはつらつとした表情を見ていると、人にはいろいろな考え方があり、大切なことはそれぞれですが、自分が心から大切だと信じる生活を日々実行できることほど幸福なことはないのだと感じてしまいました。
この人たちは天才だ!と尊敬し憧れている職種というか人たちが、僕には3種存在します。
1つ目は「漫画家」。
理由は、絵も描けてストーリーも構想できてコトバも創り出せる、という点でマルチな能力や才能が必要だと思うからです。なぜこの3つの能力を高い次元で併せ持つことができるのか・・・。不思議です。
2つ目は「作曲家」。
理由は、メロディーを産み出すということができる、という行為がもう信じられないからです。なぜメロディーが思い浮かぶのか。そしてなぜそれを譜面にかいて再現できるのか・・・。かなり不思議です。
3つ目は「棋士(将棋/チェス/囲碁)」。
僕は将棋やチェスは好きではありません。なぜなら5手先を読めないからです。というか3手先も読めません。なぜそれができるのか??全く意味がわかりません。三和物産にも将棋が好きな人がいるのですが、その人も数手先を読むというゲームを純粋に楽しいと感じているようです・・・。とても不思議です。
さて、この天才たちの中で、僕が特に尊敬し憧れている人がいます。その人は羽生善治棋士です。今は藤井棋士という若い棋士が注目されているようですが、羽生棋士は特別です。僕は将棋が好きではないので、将棋の打ち筋がどうとかはあまり興味がありません。なんというか、そのたたずまいや存在感そしてコトバに人としての深みと厚みそして孤高の厳しさを感じるんですよね。
天才ってきっと孤独だと思うんです。周りに理解してくれる人が少ないと思うから。でも天才でありながら想像力を駆使して天才ではない人の気持ちを推理し察することができる人。そんな人がきっと世界を良い方に進めてくれているのではないでしょうか。羽生善治さんはそんな天才の中の天才なんじゃないかなーって思ってます。
羽生善治語録には勇気がモリモリ湧いてくるそんなコトバがたくさんあるのですが、その中でも僕の好きなコトバを紹介して今回のブログを締めくくらせていただきます。きっといろんなことに挑戦する勇気が湧いてくるはず!ではまた!
新しい試みがうまくいくことは半分もない。でもやらないと、自分の世界が固まってしまう。
(羽生善治)
先日ふと考えたことがあります。
何かというと「趣味」についてです・・
皆さんはどんな趣味を持っていますか? 自分には趣味と言えるようなものが無いなぁ~ と気づいてしまったのです。
これは寂しい老後を送ることになると思い、ある事を「趣味」とする事にしました。
50の手習いになりますが、新しいことに楽しみながらチャレンジしてみようと!!
いつの日にか、皆さんに「こんな趣味を持っています」と言えるようになるまで張り切ってみようと思います!
皆さんも、何か新しいことに楽しみながらチャレンジしてみませんか!!
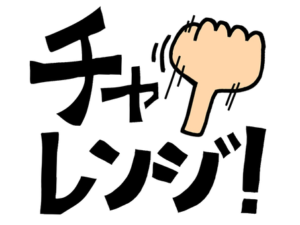
4月9日より、美味しいもなかをつくりながら
“故人への想いをひきだし、今を生きる希望をひきだす”
体験型手づくりもなかのクラウドファンディングに挑戦しています。
↓応援していただけると嬉しいです。
https://camp-fire.jp/projects/view/660847?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_sho
クラウドファンディングページに記載できなかった想いなどを書いてみたいと思います。
今回プロダクト化にあたり、20代~40代のさまざまな方にインタビューさせていただきました。
皆さんはどのように感じますか?
「おばあちゃんが急になくなり、母が半年経った今でも元気がない。私が帰省する時にこのもなか買って帰りたい。一緒にやりたい。お母さんを元気にしたい」(20代大学生)
「友人が急に亡くなった。生前、友人からは家族とは縁を切っていると聞いていたが、葬儀は地元で行うことになったようだった。知らない間に葬儀も49日も終わっていた。私の方が彼のことを分かっていたのに・・・何もしてあげられなかった後悔が今でもある」(30代会社員)
「大好きだった芸人が亡くなったことを知り、何かしたいけど、葬儀に参列できるわけもなく、気持ちの整理をつけることができない」(40代会社員)
私があらためて感じたのは、生きている限り大切な人との死別はだれもが経験するということ。
そして死別により周りに苦しんだり悩んだりしていている人がいても、何もしてあげることができないのかもということ。
死別によりモヤモヤしている方が周りにいたら、何かしてあげられる方法の一つとして、この「49日のひきだしもなか」が当たり前になる日を夢見て、まだまだ頑張りたいと思います。
- 2025.12
- 2025.11
- 2025.10
- 2025.9
- 2025.8
- 2025.7
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6