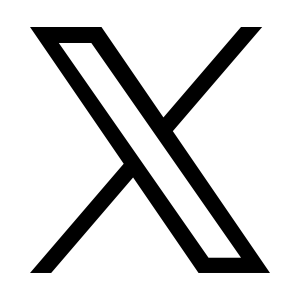LEADERS BLOG
最近、高校時代の同級生、20代の遊び仲間、前職の仕事仲間などとの飲み会の機会が何度かありました。
声をかけてもらった時は久しぶりすぎて何を話せばいいのか、話が合うのかなど迷いの気持ちがありました。
独身の人もいれば孫がいる人も、離婚している人もいました。
だいたい6〜10人程度の人数で簡単に近況を話したり、昔話を懐かしく語り合ったりするうちにその距離感はゆったりと縮まっていく時間が心地よかったです。
参加して良かったと思いました。
何十年も前の共有した時間が蘇るからか。
時間の経過が心に何かをおよぼすのか。
みなさん力みが抜けて穏やかになっているように感じられました。
その後まわりの人に今までより少しやさしい眼差しを向けられる気がしました。
そんな気持ちにさせてくれた段取りしてくれた方に感謝です。
みなさんにもおいおいそんな時が来ると思いますよ。
以前話したように元は動物は苦手でしたが、家内が野良の保護猫を引き受けたり、譲渡の手伝いをしています。
なので今は2ヶ月ほどの子猫2匹が家中を飛び回り、様々なものに関心を持ち、ブラインドやプランターを壊したりして困っています。あと大人しい看取り前の老猫もいます。
人も動物も幼い頃はいたずら好き、何にでも興味を持つのは同じなんですね。
人の子は思うようにならないと周りのことも考えずにすねたり、泣きまくります。
猫もお腹が空くとやはり鳴いてせびりますが、どうにもならないとわかると意外とあっさり諦めて寝てしまいます。
そして体調が悪かったり、病気で苦しい時でも無駄に鳴くこともなく、ただ横になっています。
亡くなる時も静かに受け入れて眠るように死をむかえることが多いようです。
その日でも、どうにか歩ければ自分でトイレに行きます。
無理に抗らうことなく自分の命を自分の力で最期まで生ききる姿が美しいなあと思います。
小松に20年近く通っている床屋があります。
川の近くの古い床屋で内装は開業した頃とほとんど変わらず、昔の髪型のポスターが貼ってあり、髪型の変遷を見ることができるレトロなお店です。
エアコンも3台目で、古いものもそのまま取り外さず残しているので、エアコンの歴史もわかります。
娘さんは50才ほどで東京で結婚されて仕事をしているようです。
私は毛が少なく、短いのでとても安く刈ってもらっています(おばあちゃんからすぐ終わるからこの値段でいいと言われました)
この前刈ってもらいながら雑談をした時に10年前にご主人が亡くなったことを知りました。
30才で脳梗塞になり、一応働いてはいたようですが不自由な生活を送っていたとのこと。
だからおばあちゃんが床屋で生業を立てていたようです。
今から思い返しても亡くなった様子は特に察知できず、てっきりご主人は奥の住まいにいるものとばかり思っていました。
お世話になっていたのに全く気づくことがなく、お悔やみの言葉をかけることもできなかったので、申し訳なく切ない気持ちになりました。
自分も含めて多くの人(ほとんどの人)が電車、バスの中で忙しなく携帯を操作している。そんな中で手に取った紙の本を穏やかな表情で静かにめくっている人を見るとなぜかホッとする。
自分もKindle はよく読みますがそれは知識や情報を得ればいい時。
私には心とつながる本は紙で作られていて、ちゃんと紙の感触も感じながらめくって読む行為が大切。
だから自分がどういう目的、どういう気持ちでその本と接したいかで自然に選ぶ。
穏やかな時間を感じ、その世界が心の奥にゆっくり入ってきてごちゃごちゃした気持ちを解きほぐしてくれるのは紙の本。
そういう時間は小さな幸せをくれる。
みなさんがホッとするのはどんな時ですか?
ある日家内がリビングの棚の上に置いてあった観葉植物を見て「花が咲いたよ、この植物は『幸福の木』て名前」と話した。
そこに観葉植物があることすらさして気にもしていなかったが、少し調べてみたら4〜10年に一度花が咲き、花が咲くと花に栄養がとられて葉が枯れるとのこと。
十分開花した状態だと1センチ程度のつくしが何十本も束ねられているような見たことがない花で少しきついがいい匂いである。
一説によると幹や葉の伸びやかな美しい佇まいから「幸福」「金運」「仕事運」が高まると言われているらしい。
※花言葉はどれも先に言った者勝ち。
しかし花が咲くと葉は枯れてしまう、よく考えれば多くの草はそんなもので花から実をつくり命を繋いでいく。
「幸福の木」なのに葉を生かすために花を切ってしまうことは自然の摂理に反する行為に思える。
まさに人が「観葉植物」を造ったのだと思った。
- 2025.12
- 2025.11
- 2025.10
- 2025.9
- 2025.8
- 2025.7
- 2025.6
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6