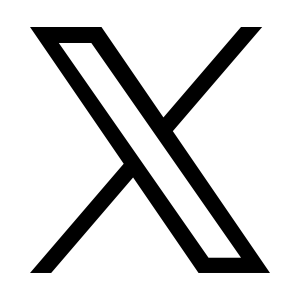LEADERS BLOG
私たちは今期より商品開発に力を入れ、部署混合のプロジェクトチームを複数立ち上げて定期的にミーティングを開催しています。(オンラインが定着したメリットで容易に遠方の部署同士が集まり、議論できる!)
まだまだ手探りですが、だんだんアイデアが生まれて、それに対する意見も発信されるようにもなり、話し合うことの大切と楽しさをみんなが感じ始めています。
誰かのアイデアに対して良さそうかなと思い、飛びついても、じっくり考え、市場の声を冷静に捉えことができるようになるといろいろとまずい点が見えてきてそのアイデアがオクラ入りになることがあります。
2歩進んだと思ったら4歩後退りのようなことがたびたびです。
一人で進めていると後退りは心理的にきついですが、仲間と進めていると本質に近づける議論ができていると考えることができて、次のステップに登っている、と捉えることができます。(実は辛いことも多い、、、)
そしてリーダーは自分の仕事が忙しい中、みんながアイデア創出できるツールや仕組を日々考えています。
商品開発していく中でみんなで学び、悩み、楽しみ、ミッションを実現できる商品開発の階段を少しづつ登って行きます。
さらに明確なコンセプトを大事にしつつみんなで様々な議論を進める中で発見があり、進化していくようなもの創りに挑み、売上に寄与する商品と共に目先に捉われない革新的な商品開発の両方を追求します。
そして直接開発に関わらない人たちもなんらかの形でプロジェクトに関わり、全員でのもの創りが企業風土になっていくことを目指します。
先日遺影写真家のドキュメンタリーをテレビで見ました。
以前は広告の写真を専門にされていた方なのですが、販売商品が終わると共に消えていく写真よりずっと残り見続けてもらえる遺影専門となりました。
義理のお父さんが亡くなった時に、その方が撮影した写真がなく、旅行に行った時の誰が撮ったかわからない写真を使うことになり、自分はプロなのにと、、、とても後悔が残ったそうです。
そのあと直ぐにご両親の写真を撮り、話しかけてくれるような写真が仕上がったことがきっかけということです。
そして遺影に向かえば声が聞こえる、口角を上げただけではなく目が自然に笑っているそんな人の心に残る写真を撮りたいと強く思うようになったそうです。
写真家の名前は残らないが写真そのものは100年後にも残る。
故人が伝わる。
残されたひとを癒す。
写真を見る=亡き人に会うと感じられる。
そんな遺影写真。
遺影写真を撮られた方はこれまでのケジメになり、残された人生の再出発になったと話されていました。
遺影の中の明るい自然な自分の顔を見て元気でいようと思うそうです。
生きる力をくれる。
自分の笑顔は自分に元気をくれる。
私たちの仕事も直接ではありませんが故人や遺族に寄り添う仕事です。
余命わずかな人と接していく仕事って辛いという先入観を拭いさり、こんな「仕事」って本当につながりを大切にしているんだと感じました。
自分の大切にすることとつながっている仕事で生きていけることのありがたさに満ちた人でした。
自分たちの仕事がこんな姿に少しでも近づければいいなぁと思いました。
従兄弟のお墓参りに、彼の両親(=私の叔父さん、叔母さん)と私の妹とで行ってきました。
神奈川県の県道から2~3分登った丘にその霊園はあり、周りは林で囲まれていて少し俗世とは離れている感じで、通路のようなタイルの壁の前に1.4メートル程度の高さの洋風の墓石が並んでいるという、これまで見たことのない明るい印象の作りでした。
手を合わせている時にその墓石にトンボが止まって、妹が「〇〇ちゃんだ」と言います。
そんなことはあるはずがないのですが、そうかも・・・と思わせる何かを感じました。
その後4人で簡単に食事をして、なんとはなくその従兄弟の昔話になりました。
それは我々が子供の頃から成人するまでの昔話がほとんどでしたが、かなり鮮明に思い出せたことがいろいろとあります。
叔父さん叔母さんにとっては、自分たちより早く亡くなった子供の哀しい想い出ですが、妹は明るく話し、叔父さん叔母さんはそれをニコニコして聞いていました。
お墓参りという行為で亡き人を思い出し、共にお参りした人と語り合うことで、もう会えない人の記憶とつながることができました。
少し前に会社の会議で
「人は二度死ぬ、1回目は死んだ時、2回目は忘れられた時」
という話を聞きました。
その言葉が蘇ります。思い出すうちは、その人の中でヒトは生きている。
今回のお墓参りで、とても分かった気がします。
先週、西荻窪の貸しギャラリー「ステラ」で着物ヤーンの展示販売会が開催されました。
新しさとレトロさが混在し、入ってみたい呑み屋さんも何件かあり、居心地が良さそうな素敵な街でした。
その街にぴったりの3坪くらいの小さいけれど街に溶け込んだギャラリーには5人のお客様が商品を興味深げに見入っていました。
着物ヤーンを活用した商品やアクセントに使っている様々なアイデア商品やハンドクラフト商品が所狭しと並べられていました。
その中に商品や着物ヤーンを選んでいる5歳くらいの女の子とお母さんがいました。
お店の人(藤枝さん)が「こういうのも作れますよ」と話しかけるとその女の子はお母さんとお店の人の顔を交互に見ながら興味深々という様子で聞いていました。
そしていくつかの商品を買い求めて、お母さんと手を繋いで嬉しそうに帰って行きました。
お母さんが子供のために作ってあげる、子供はそれが出来上がるのをワクワクしながら隣で待ちわび、嬉しそうに身につけ、大切にする。
着物ヤーンを使ったたった一つのお母さん手作りの一品。
(私も小学生の時におふくろが手作りしてくれた胸にY(良成のY)と縫い込んだ青いセーターをよく着て学校に行ったことを思い出しました。友人がいいなぁと思ったらしく彼のお母さんに作って欲しいと頼んだということを聞いて少し誇らしかったです)
子供と親の気持ちをつなげるそして小さな想い出をつくるお手伝いができるってとてもあったかいことだと感じました。
先日葬儀社様と御遺族との商談のお話を聞く機会がありました。
お葬儀プランの御遺族への説明の様子をお聞きして、心情に配慮しながらとても考えられて商談にのぞんでいることが理解できました。
葬儀社様が故人様の人となりを十分お聴きし、ふさわしい提案を行い、御遺族はこれでいいのか少し不安を抱きながらも、会葬者の方々から選んだプランや棺などが認められると自分の選択が間違えていなかったとやっと安堵し、自分を肯定することができるようです。
そのことを聞いて葬儀社様も勧めて良かったと仕事の喜びを感じ、また自信を持ってそのプランや商品をおすすめできるそうです。
我々はそのお話を聞いて採用頂いた商品への想いが高まり、更に開発への意欲がわきます。
その想いにより別れのシーンを思い浮かべる想像力が向上して出会うことのない
会葬者、御遺族→葬儀社様→三和
のつながりが生まれるような気がします。
会えない人とのつながりに想いを馳せ、想像するって我々のものづくりの原点なんだとつくづく感じました。
- 2025.5
- 2025.4
- 2025.2
- 2025.1
- 2024.12
- 2024.11
- 2024.10
- 2024.9
- 2024.8
- 2024.7
- 2024.6
- 2024.5
- 2023.12
- 2023.11
- 2023.10
- 2023.9
- 2023.8
- 2023.7
- 2023.6
- 2023.5
- 2023.4
- 2023.3
- 2023.2
- 2023.1
- 2022.12
- 2022.11
- 2022.10
- 2022.9
- 2022.8
- 2022.7
- 2022.6
- 2022.5
- 2022.4
- 2022.3
- 2022.2
- 2022.1
- 2021.12
- 2021.11
- 2021.10
- 2021.9
- 2021.8
- 2021.7
- 2021.6
- 2021.5
- 2021.4
- 2021.3
- 2021.2
- 2021.1
- 2020.12
- 2020.11
- 2020.10
- 2020.9
- 2020.8
- 2020.7
- 2020.6
- 2020.5
- 2020.4
- 2020.3
- 2020.2
- 2020.1
- 2019.12
- 2019.11
- 2019.10
- 2019.9
- 2019.8
- 2019.7
- 2019.6